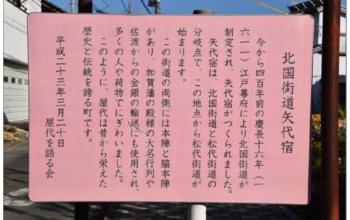おじょこな800字小説
第二十六回「散骨」
作・塚田浩司
雅美は白い小瓶を開け、その中身を海に放った。白い塊が海に落ち、白い粉が辺りを舞った。雅美は水面がわずかに揺れるのを見ながら手を合わせた。小瓶の中身は夫のお骨だった。
波に流され、夫の骨はもう見えない。これで役目を終えた。雅美は隣にいる息子の幸良をチラッと見た。幸良は一言も言葉を発することなく、手を合わせるでもなく、ただ遠くを見つめていた。
海からの帰り道、車内で幸良に声をかけられた。
「アイツが海好きだったなんて意外だったな。しかも死んだら海に散骨してくれって母さんに頼んでいたなんて。パチンコと酒にしか興味がないと思っていたよ」
アイツとは夫のことだ。父親らしいことは何一つしてこなかった夫が、幸良からアイツ呼ばわりされるのも無理はない。ひどい父であり、ひどい夫だったから。
「でも、母さんは人が良すぎるよ。あんな奴の望みなんて叶えてあげることはなかったんじゃないの? あんなに辛い目にあったのに」

幸良の視線を感じた。おそらく昔、夫からの暴力によってつけられた、こめかみの傷を見ているのだろう。
「一応夫婦だしね」雅美はポツリと呟いた。そして、夫と付き合い始めた頃を思い出した。
アルコール依存症になる前の夫は、部屋の隅の狭い空間で本を読んでいるような物静かな人だった。当時、そんな夫があることを雅美に打ち明けた。
「子供の頃、家族で船旅をしたんだ。そしたら転覆してさ。わずかな時間だったけど海に放り投げられたんだ。すぐにボートで助けてもらったけどね。でも、それ以来、海が怖いんだ。海だけじゃなくて広いところと水がね」
窓の外を見ると、青い海が見えた。
雅美は運転している息子の隣で海を眺めながら想像した。今頃、あの人は広大な海の中で彷徨っているのだと。