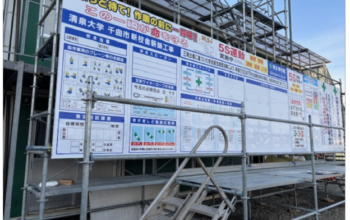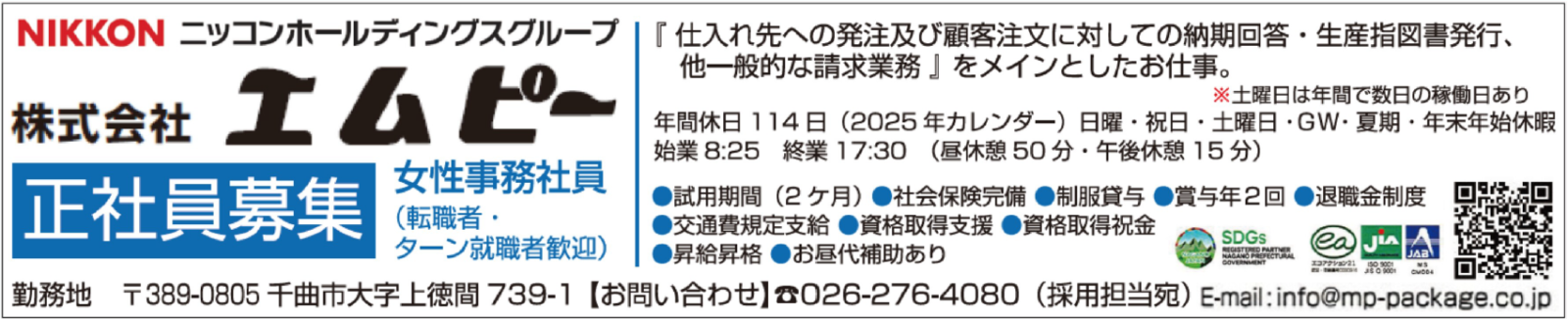おじょこな800字小説 第四十八回「そばにいたいだけ」
彼と付き合ってから一ヶ月が経った。
下校はいつも一緒で、彼はいつも将来の夢を熱く語る。
「将来は父さんを超える蕎麦職人になる。それで、うちの店を日本一の蕎麦屋にするんだ」
まるで小学生が夢を語るみたいにまっすぐな彼の瞳はとても魅力的だ。
彼を好きになってよかった。彼のそばにいられて幸せだと思える瞬間だった。
でも、彼の夢を聞きながら喉の奥が痒くなるのを感じていた。その理由は、おそらく彼の制服に蕎麦粉が付着しているからだと思う。
量にすれば、ほこり程度でも私の体は反応してしまう。
幼い頃から、「発作が起こるから蕎麦屋さんの前は通らないようにね」とお母さんから注意されていた。そんな重度の蕎麦アレルギーの私が、蕎麦職人を目指している人と付き合っている。
「ねえ、手を繋いで帰ろうよ」
何度か彼から手を差し出されたことがある。顔を赤らめながら言う、彼がたまらなく愛おしかった。それに差し出された彼の細くてきれいな指を見ると胸がドキドキした。
本当は私も手を繋ぎたい。だけど、私は首を横に振る。だって手なんて繋いだら私は……
彼から手を差し出されたのは一度や二度ではない。
最初は「もったいぶるなあ」と彼は笑っていたけど、それが何度か続くと、彼は悲しい目をするようになった。そして、ここ最近は手を差し出してくれることもなくなった。
もしかしたら、彼とは結ばれない運命なのかもしれない。彼の悲しそうな目を見るとそう思わずにはいられなかった。
日曜日に彼とデートすることになった。私服の彼は新鮮で、ついつい見惚れてしまう。
話題の映画を見に行った後、パスタ屋さんでランチを食べに行った。
お店でパスタを食べながらも彼は蕎麦について語った。卒業後は蕎麦屋の名店で修行するらしい。そして、いつかは家の蕎麦屋を継ぐんだと熱く語った。
その話を聞きながら私は彼の蕎麦屋さんで女将さんをしている姿を思い浮かべた。彼の打つお蕎麦を私がお客さんに運ぶ。お客さんは「美味しい」と喜び、私たちも笑顔になる。想像だったらいくらでもできる。でも、現実的にはそれは無理だ。お蕎麦屋さんに入った時点で私の体は苦しくなってしまう。目の前のパスタを見て、もし、彼がイタリアンのシェフを目指してくれたならなあと強く思った。
パスタ屋さんを出ると、彼は久しぶりに「手を繋ごうよ」と手を差し出した。彼の声が震えていた。
胸が痛んだ。彼は声を震わせるほどに勇気を振り絞ったのだと思う。その気持ちに答えたい。いっそのこと発作が起きてもいいから彼の手に触れてみたい。細くて長い指に自分の手を絡ませてみたい。
だけど、そんなことをすれば私は‥‥‥。
頭の中で二つの考えがせめぎ合った。どうすることもできずに固まっていると、ついに彼は無言のまま手を引っ込めた。そして、
「ねえ、本当に俺のこと好き?」と彼は私の目を見ずに言った。
「もちろん、好きだよ」と私はすぐに返した。だってその気持ちに嘘はなかった。
「じゃあ、どうして?俺たちもう付き合って一か月も経つのに手も繋がせてくれないじゃあ。そんなの付き合ってるって言えるのかなあ」
彼の唇が震えていた。悲しみと怒りが混じった顔。こんなの、私の好きな彼の表情じゃない。
もう本当のことを言おう。そもそも、私は考えすぎていたのかもしれない。案外真実を告げれば「なんだそうだったんだあ。早く言えよ」と笑ってくれるかもしれない。優しい彼のことだから、そのことで私をフったりはしないはず。だけど、彼の夢はどうなるんだろう。私が蕎麦アレルギーだって告白したら、彼は夢をあきらめてくれるのだろうか。私との将来を選んでくれるのだろうか。もういいや。考えれば考えるほどわからなくなる。一か八かの賭けに出てみよう。
「本当は……」
次の言葉が出ない。悲しそうな彼の顔がそうさせているのだと思った。
今わかった。私が好きなのは将来の夢を真剣に、そして嬉しそうに語る彼だ。
「ごめんね、本当は、そんなに好きじゃなかったかも。最初はいいと思ったけどさあ、君と一緒だと面白くないんだよね。学校の帰りも蕎麦の話しかしないしさ、なんかそういう熱い感じ私は無理だな。だからその……」
私は一気に言葉を吐き出し、彼に背を向けた。そして彼の反応を待たずに歩き出した。
少しでも彼から距離を取りたくて、速足で歩いた。我慢していたけど、デート中もずっと喉の奥がかゆかった。彼から離れればそれも治るはず。
でも、おかしいなあ。彼はもう近くにいないのに発作みたいに息が苦しい。目から涙もあふれ出てくる。なんでアレルギーの症状が……
そうか、私は悲しいんだ。どうしようもないくらい悲しいんだ。そんな簡単なこともわからないくらい私は悲しいんだ。
ただ彼のそばにいたいだけなのに。どうしてそんな簡単なことが叶わないんだろう。
すれ違う人に泣き顔を見られないように顔を両手で隠しながら家まで歩いた。

著者紹介
塚田浩司/柏屋当主。屋代出身。