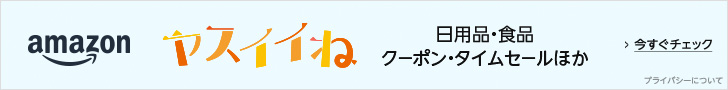特集2 千曲市の図書館③ ◆学校図書館の司書の待遇改善を
◆千曲市立図書館と学校図書館の「連携」
千曲市の小中学生の読書活動を支援するために、市内の更埴、更埴西、戸倉の市立図書館と小学校、中学校の学校図書館が一体となって、必要な資料を提供する仕組み「ブックネットちくま」がある。
市立図書館のホームページによると、各図書館は同じ図書館システムで結ばれており、資料の検索から貸出の申し込みを一括で行うことができる。各学校図書館の平均蔵書冊数は13000冊だが市立図書館を合わせると約44万冊の蔵書となるという(ちなみに更埴図書館は24万冊の蔵書がある)。こうした蔵書の中から、児童や生徒が学びや読書活動を推進するため、各図書館は協力、連携して図書や資料の提供に努めている。
例えば、ある小学校の5年生23人のクラスで「大豆からどのように豆腐をつくるか」のテーマを調べたいとき、図書館に問い合わせると参考になる図書を市内図書館の蔵書から検索して、23冊の同じ図書をそろえることができる。実際に「大豆から豆腐の作り方」のほか、「新聞の製作」などの図書のリクエストがあったという。
このほか、移動図書館についても、市立図書館のホームページには「更埴図書館みどり号巡回日程」が掲載されている。保育園児、児童、生徒をはじめ、手続きをすれば一人10冊まで市民に広く活用できる。読書好きには魅力的な移動図書館だ。
市立図書館、学校図書館では、児童・生徒の皆さんに図書館を活用してもらい、いろいろな本と出会って、いろいろな世界への扉を自ら開いていってもらいたいと願っているはずだ。
◆学校図書館司書 低賃金・不安定な雇用 待遇改善が急務
学校図書館の実態はどうなのだろう。教育現場に詳しい関係者によると、長野県内の学校図書館の司書のほとんどが非正規雇用、パートといった雇用で、時給は低く、フルタイムで働いても給与は厳しいという。こうしたデメリットを踏まえて、それでも図書館の仕事に情熱を持っている司書の方もいる。しかし、国の定める規定が「壁」となっている。現実的な厳しさから、学校図書館の機能は低迷しつつある。
それでも政府・文部科学省は最近、「学習の場」として図書館の機能を見直す動きもあるが、学校図書館の司書の待遇改善が最優先の課題だろう。小中学校の「保健の先生と図書館の先生」はなくてはならない存在だと信じている。このままの厳しい学校図書館のままでは、「知の拠点」は崩れていってしまう。
(特任記者・中澤幸彦)
戸倉上山田中学校図書館(ホームページ施設紹介より)