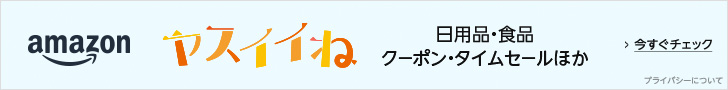北国街道 歴史こぼれ話(第2回) 明治天皇巡幸その一(鼠宿)
参勤交代や善光寺詣ででにぎわった北国街道も明治の時代へと移る。戊辰戦争の際には北越に出兵する松代藩ら官軍が北国街道を進軍し、沿道の人々も人夫に駆り出された。
維新後新政府は徳川将軍家に代わる天皇の威光を人心に知らしめるため、明治天皇の全国巡幸を計画(六大巡幸)。明治11年(1878)には北陸・東海巡幸が行われ、9月6日に右大臣・岩倉具視以下官員839人、人足およそ1000人を従えた大行列が碓氷峠を越え信州に入った。8日朝6時、上田の上田街学校に宿泊していた一行は長野を目指し出発。一日で40キロを移動する行程のため、街道筋には事前に何か所か「御小休所(おこやすみじょ)」が設けられた。いまも各地には昭和初期に建立された御小休所や御膳水の場所を示す碑が残されている。
南条では松代藩産物会所として使われていた滝沢邸で小休止を行った。この日は大変暑い日で、午前7時半頃に到着したが、供奉員はしきりに氷を求めたとの記録が残る。屋敷は現存しており、邸内には天皇に提供された御膳水の井戸があるが、私有地のため非公開。(続く)
明治天皇御小休所として使用された松代藩産物会所