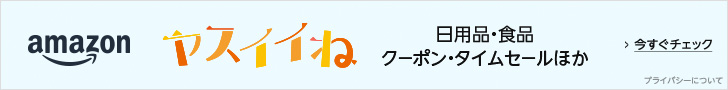特集① 清泉大学農学部設置協議会 2回目で実質的な議論
◆校舎は北野建設グループが設計建設
この4月から共学となった清泉大学(長野市)は7月14日、2027年4月に千曲市に開設する農学部の「設置協議会」を長野市の同大東口キャンパスのピラール館で開いた。2回目となる協議会では冒頭、田村俊輔学長が先に亡くなったローマ・カトリック教会のフランシスコ教皇の地球温暖化を懸念して環境保護を訴えた精神を踏まえて、「地球の姉妹(植物を含む生物)と共存して、地球を守る農学部の創設にむけてしっかりとやっていきたい」と決意を述べた。田村学長は先の農学部創設の構想発表の記者会見で「長野県の農業の課題や強みを鑑みて、長野ならではの農学部をつくりたいと考えた」と語った。
協議会の座長役を務めるホクトの水野雅義社長は「長野県だけでなく、それ以外の多くの方に関心をもってもらいたい、より盛り上げていきたい」と意欲的に語った。協議会には、ホクト、藤屋、サンクゼール、R&Cながの青果のほか、千曲市から「醤油豆」で知られる高村商店、「木の花屋」(このはなや)の宮城商店、清酒「姨捨正宗」の長野銘醸の3社を含む12社などが参加。協議会の前半は初めてメディアに公開された。
☆設計建設は「アーキプランと北野建設」グループ
法人本部の経営企画室の発表によると、来年1月に着工予定の校舎の建設事業者は6月に実施された一般競争入札の結果、設計がアーキプラン(長野市)、建設施工が北野建設(同)の北野建設グルーブに決定した。すでに建設の準備が進められている。
建築費用は約30億円、資金は国の「大学・高専機能強化支援事業」の補助金12億数千万円、清泉大の自己資金と融資で約9億円、千曲市などから補助金8億円(今後、補正予算を検討する)。キャンパスは旧更埴庁舎跡地を予定している。敷地面積は約3760平方メートルで、現在旧庁舎の解体工事を進めている。実習に使用する農地やハウスなども千曲市内で確保する方針だ。
☆「農・地域共創コース」と「食品・発酵コース」に
協議会で発表された農学部のコースは2つ。当初の地域創成コースは「農・地域共創コース」に、農芸化学コースは「食品・発酵コース」に名称を変更する。定員は85人。
「農・地域共創コース」は、農業の理論や実践に加えて、経営も学ぶことで農学をベースに地域の課題解決に貢献できる人材を育成する。地域振興を図る「長野モデル」の実現を目指す。
「食品・発酵コース」は、長野県が誇る味噌や日本酒、ワインなど、発酵や醸造を学び、その発展やマーケット拡大に貢献する人材を育てる。
両方のコースともに、環境に配慮し、持続可能な食料供給システムの構築を目指せる人材育成を共通の目的とする。
☆プレキャンパスで市民にアピール
清泉大は千曲市と共催で、9月20日(土)に「市民参加型」のプレオープンキャンパスを「信州の幸(めぐみ)あんずホール」で行う。市民に、農学部の学びの内容を知ってもらうのが目的。このほか、27年4月の農学部開設に向けて、高校生に入試情報や個別相談の機会も提供する。
また子供から大人まで楽しめるイベントとして、「千曲市クイズ王決定戦」(成績上位者には景品)や、中学生向けに「大学の歩き方」の説明会や「こども科学実験」「VRゴーグル体験」といったイベントも実施する。
協議会のメンバーや千曲商工会議所の会員らによる「試飲、試食、商品販売」もあんずホールマルシェとして行う予定。
清泉大は農学部開設に向けて、24年2月に文部科学省の「大学・高専機能強化支援事業」に申請し、6月26日に採択された。同大は25年4月に全面共学化に踏み切るなど厳しい経営環境を受け大学改革に取り組んでいる。
(特任記者・中澤幸彦)

協議会で挨拶するホクトの水野社長
(7月14日 長野市の長野駅東口近くの清泉大「東口キャンパス」ピラール館I階で)

(写真上)昭和41年建築 旧更埴庁舎千曲庁舎の新築により昨年解体された
(写真下)現在の清泉大学長野駅東口キャンパス